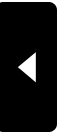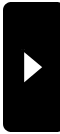今年読んでよかったおすすめ本ランキングトTOP5〜アウトドアからビジネス書まで
こんばんはーぴのこです。
今年読んでよかったおすすめ本TOP5をご紹介します。
最近、本たくさん読むんですよね。年間100冊くらい?斜め読みの多動ですが。ジャンルも色々。漫画は今年はあまり読まなかったかな。
今年はビジネス書から、ブッダの呼吸の本から、SNS運用の本とか、へそくり生活とか、料理の本とかまあまあ、色々と読みましたね(汗)アウトドアでは、GO OUT!とか、BE PALとか色々雑誌は結構読んでいます。(d magazineで) 最もたくさん読んでいる、がちなマインドフルネス本や心理学の本は除外しました。マニアックすぎるので(汗)
では、続々ご紹介しましょう。

一周回って、また冬キャンプにときめいてしまった特集。大好きなフォトグラファーの島津和貴さんの写真が多いからかもしれないけれど、
久しぶりに冬キャンプの写真撮りたいなーの気持ちが湧いてきました。
ときめいて、ランタンハンガーも買ってしまったという・・・ こちらはフィールドデビューしたらご紹介いたします。週末は寒いところに行く予定。

次はビジネス書!
最近読んだので、記憶に新しいのもあるですが、わかりやすく、どうすればよいチームが作れるのかが書かれていた本でした。
来年から今いるチームが少し大きくなりそうで、どうやってまとめていこうかな〜と思っていたので、読んでいていろいろなヒントで、目から鱗。
リーダーは、ファシリテイター!とか、やりとりは原則1on1で聞くとか、ミッション・ビジョンに基づいてみんながやる気をだせるチームづくりが大切というようなお話でした。
筆者のチーム・ビルディングの紹介の仕方が、めちゃくちゃわかりやすくって、ぐいぐい読めました。もう一冊読んでる。
要約:
・リーダーは、メンバーを活かすのが仕事そのために、フラットな場をつくる
・そして、メンバーの想いや考えを聴く
・会議の場でもフラットに意見を出し合う
・チームはゴールを共有しているからチームなのだ
・そして、それは組織をまたがる場合も同じ踏み出し、続けることが大事
・ヒエラルキーではなく、フラットであれ
・自分ではなく、メンバーを活かそう
・そのために話を聴こう
伊藤羊一. 「僕たちのチーム」のつくりかた メンバーの強みを活かしきるリーダーシップ (Japanese Edition) (p.180). Kindle 版.

はい今度は、子育て本ですー。
この本の著者の一人、ダニエル・シーゲルはUCLAの精神科臨床教授で、脳科学とマインドフルネス業界でも第一人者。
マインドフルネスと愛着の子育てを提唱している方です。
もう、首がもげそうな位にうなづいてしまった。この本は読んだほうがいいです。子育てで一番大事なのは、良い大学にいれることではありません、愛着ですよー。
「子どもがどう育つかの最もよい判断材料は、少なくとも1人の大人と確かな愛着を築けたかどうかであることがはっきり示されている。」
子育てに必要な4つのS
第1のS(Safe──安全であること):親の最初の仕事は子どもの安全を守ることなので、これが確かな愛着を育むための第一歩だ。
第2のS (Seen──見守られていること) 子どもが見守られていると感じられるようにすること。子育てで重要なのは、とにかく子どもに寄り添うことに尽きる。子どもの発表会に出席し、いっしょに遊び、本を読み、ほかにもたくさんのことをして過ごすこと。
第3のS (Soothed──なだめられていること)親は子どもに、安全で、見守られていると感じながら、つらいときにはなだめられていると感じてもらいたい。子どもをなだめるとは、人生の海で必ず襲いかかってくる波を消し去ることではない。押し寄せてきた波に乗る方法を教え、子どもから必要とされたときそばにいることだ。
(感想:そうなんですよね。だから、ストレスや失敗しそうな状況をすべて取り除くことがいいわけでもないので、安心して失敗させてあげて、転んだらなぐさめることが大切ってことですかね〜)
第4のS(Secure──安心していること)安全で、見守られ、なだめられていると感じていれば、第4のS(Secure──安心していること)、つまり安心感につながる
いつでも寄り添ってくれると〝子どもが当てにできる存在〟になろう。あなたが、安全を守るためになんでもしてくれる、見守るために懸命に努力してくれる、思いどおりにいかないときにはそばにいてなだめてくれると信じられるようになれば、安心感が生まれるだろう。
「4つのS」は、子どもの脳を統合へ導き、柔軟性がある、ストレスを受けにくい神経系を構築する。結果として、子どもは、自分が安全で、豊かな人間関係と愛に恵まれ、避けられない困難にもうまく対処できると信じて、まわりの世界に安心と居心地のよさを感じながら生き抜く力を身につけていける。
ダニエル・J・シーゲル,ティナ・ペイン・ブライソン. 生き抜く力をはぐくむ 愛着の子育て (Japanese Edition) (p.27). Kindle 版. より引用
ということで、子どもに安全を提供して、間違った時失敗したときにはなだめて、手を出し過ぎず、安心を提供できる親になりたい!そう思いました。そのためには、親のエゴを満足させるためや、感情調整のために子供を利用してはならず、親も夫婦同士で、支え合うなどの愛着を大切にしていかないと寄り添えないですよねー。もうこの本は、最先端の知見プラスわかりやすいので、今年の子育て本としては、ずば抜けて1位でした。

この本では、現代人が野生に戻る必要性を伝えておりその手段として、科学が教えるトレイルラン、低炭水化物食、マインドフルネスなどがあると述べています。登山・キャンプ・マインドフルネスを愛するぴのことしては、「私の好きなことに科学的に証明されているなんて!」という感じで感激しながら読みました。が、食事についての記述が多いのですが、ちょっとついていけなくて、低炭水化物食の話は華麗にスルーします(爆)
”最も重要な事実として、人間には生来、治癒力がそなわっていて、体は自ら病気を治せるのだ。つまり体には恒常性維持機能──生活上の労苦やストレスから体を回復させる複雑に入り組んだ機能──がそなわっている。それこそが、本書が言う「ゴー・ワイルド」の根幹なのだ。”
”今日わたしたちを苦しめている病の大半は、この文明病なのだ。”
"「野生」。それを今わたしたちは必要としている。"
ジョンJ.レイティ,リチャード・マニング. GO WILD 野生の体を取り戻せ! 科学が教えるトレイルラン、低炭水化物食、マインドフルネス (Japanese Edition) (Kindle の位置No.85-88). Kindle 版.
こういう時に気になるのが、ジョン・レイティーは、何者か?ということですよね。ハーバード大学医学大学院臨床精神医学准教授。神経精神医学の世界的な専門家ということですよ。信頼できそうじゃないですか。この先生は、運動こそが脳を鍛える!といった本も書いていましたね。
要するに、トレイルランやマインドフルネスで、野生の感覚を取り戻すと、より自然に・幸せに生きられるよという話でした。ボリューミーな本ですが、ご興味ある方は是非読んでください。別にトレランしなくても、キャンプで、歩くもとってもいい!んじゃ?と自分たちのやっているキャンプ・登山が正当化されるそんな本でした。食事のところは、スルーしちゃったので、中性脂肪も高いし、もう一度読もうかなあ・・・

最後は、心理的安全性です。もっといろいろ日本人が書いたわかりやすそうな本がでてますが、この本が、一番有名のようですね。
心理的安全性とは、大まかに言えば「みんなが気兼ねなく意見を述べることができ、自分らしくいられる文化」のことだ
要約:
2016年2月に『ニューヨーク・タイムズ・マガジン』にチャールズ・デュヒッグが記事を書き、「最高のチームをつくる要因は何か」を突きとめるためのグーグルでの五年にわたるプロジェクトを発表した。プロジェクト・アリストテレスというコードネームがつけられた。研究者たちは、5つの成功因子をみつけたが、その中でも「心理的安全性の重要性は群を抜いている」という結論に達した。
職場で従業員が本心を言わない(懸念や疑問を口にしない)のがおきまりのパターンであること、さらには、そのような人間らしい無意識にしてしまう反応が、およそどんな組織においても仕事の質に深刻な影響を及ぼしかねない。
いろいろな企業の心理的安全性が低いためにに起こった企業の失敗例が多数掲載されています。
フォルクスワーゲン社の不正、ウエルズ・ファーゴ、ノキアなどに起こった問題の背景は・・・・他のものは優れているのにもかかわらず、
「欠けていたのは、リーダーシップだ──心理的安全性が確実に職場に広がり、人々が社内の有力者に、本当のことを話せるようにするリーダーシップである」
福島原発の事故も、事前に危険性を予期していた報告がいくつかあったのに、その懸念を軽んじてしまった経緯があるんですって。
エイミー・C・エドモンドソン,村瀬俊朗. 恐れのない組織「心理的安全性」が学習・イノベーション・成長をもたらす (Japanese Edition) (p.111). Kindle 版.
まとめると、心理的安全性とは、職場の人間関係をのらりくらり仲良くするためのものではなく、いざ、大きな失敗がもたらされそうな時、その失敗について気づいた者が、上司などからの重圧にまけず「正直に話し出せるかどうか」「それを認める風土があるかどうか」であり、それによってより生産的な方向にシフトしていく可能性をもたらす重要なファクターということ。
ということで、最後は重たいテーマになってしまいましたが、むむむこれってすごく大事!。破壊王はなぜか英語で読んでて、私も日本語で読んで(無駄な書籍代)なんか二人で「大切な一冊だったね」と感想を語り合った一冊でした。方向性として失敗しそうなのに、上に忖度して、意見がいえない。そんな組織はもう時代遅れ・・・ということでしょうか・・・。
小さなチームでも、思ったことが自由にいいあえて、否定されない。特に自分が間違った方向に行きそうな時に、それを言い合えるそんなチームを来年は仕事で作っていきたいなーと思いました。それに加えて、インクルーシブ・ダイバーシティーそんな価値観を私は大切にしていきたい。
ということで、ぴのこの今年の5冊は、こんな感じでした。アウトドア大してないじゃん・・そう思われた方もいらっしゃったかもしれません。
まあ、色々読んでインパクトが残ったのがこうだったのよね、いうことで、最後までお読みいただきありがとうございました!
*インスタやってます。気軽にフォローお願いします。右サイドバーにアイコンあります。
登録してみました。よかったらクリックお願いします!↓

にほんブログ村
今年読んでよかったおすすめ本TOP5をご紹介します。
最近、本たくさん読むんですよね。年間100冊くらい?斜め読みの多動ですが。ジャンルも色々。漫画は今年はあまり読まなかったかな。
今年はビジネス書から、ブッダの呼吸の本から、SNS運用の本とか、へそくり生活とか、料理の本とかまあまあ、色々と読みましたね(汗)アウトドアでは、GO OUT!とか、BE PALとか色々雑誌は結構読んでいます。(d magazineで) 最もたくさん読んでいる、がちなマインドフルネス本や心理学の本は除外しました。マニアックすぎるので(汗)
では、続々ご紹介しましょう。
5位 MOMO vol.26 冬キャンプ!

一周回って、また冬キャンプにときめいてしまった特集。大好きなフォトグラファーの島津和貴さんの写真が多いからかもしれないけれど、
久しぶりに冬キャンプの写真撮りたいなーの気持ちが湧いてきました。
ときめいて、ランタンハンガーも買ってしまったという・・・ こちらはフィールドデビューしたらご紹介いたします。週末は寒いところに行く予定。
2018/12/21
こんばんは〜、ぴのこです。さて今日は、雪中キャンプを楽しむ5つの秘訣ということで・・・え?まるで、◯inataの記事みたい?そういえば、◯inataのライターやめたのかって? 休止中です・・誤字脱字なく、文章を書くのが思いの他大変で! 試験中でもあったので休止してます〜我が家の雪中キャンプ…
4位 僕たちのチームのつくりかた 伊藤羊一

次はビジネス書!
最近読んだので、記憶に新しいのもあるですが、わかりやすく、どうすればよいチームが作れるのかが書かれていた本でした。
来年から今いるチームが少し大きくなりそうで、どうやってまとめていこうかな〜と思っていたので、読んでいていろいろなヒントで、目から鱗。
リーダーは、ファシリテイター!とか、やりとりは原則1on1で聞くとか、ミッション・ビジョンに基づいてみんながやる気をだせるチームづくりが大切というようなお話でした。
筆者のチーム・ビルディングの紹介の仕方が、めちゃくちゃわかりやすくって、ぐいぐい読めました。もう一冊読んでる。
要約:
・リーダーは、メンバーを活かすのが仕事そのために、フラットな場をつくる
・そして、メンバーの想いや考えを聴く
・会議の場でもフラットに意見を出し合う
・チームはゴールを共有しているからチームなのだ
・そして、それは組織をまたがる場合も同じ踏み出し、続けることが大事
・ヒエラルキーではなく、フラットであれ
・自分ではなく、メンバーを活かそう
・そのために話を聴こう
伊藤羊一. 「僕たちのチーム」のつくりかた メンバーの強みを活かしきるリーダーシップ (Japanese Edition) (p.180). Kindle 版.
3位 愛着の子育て 生き抜く力をはぐくむ

はい今度は、子育て本ですー。
この本の著者の一人、ダニエル・シーゲルはUCLAの精神科臨床教授で、脳科学とマインドフルネス業界でも第一人者。
マインドフルネスと愛着の子育てを提唱している方です。
もう、首がもげそうな位にうなづいてしまった。この本は読んだほうがいいです。子育てで一番大事なのは、良い大学にいれることではありません、愛着ですよー。
「子どもがどう育つかの最もよい判断材料は、少なくとも1人の大人と確かな愛着を築けたかどうかであることがはっきり示されている。」
子育てに必要な4つのS
第1のS(Safe──安全であること):親の最初の仕事は子どもの安全を守ることなので、これが確かな愛着を育むための第一歩だ。
第2のS (Seen──見守られていること) 子どもが見守られていると感じられるようにすること。子育てで重要なのは、とにかく子どもに寄り添うことに尽きる。子どもの発表会に出席し、いっしょに遊び、本を読み、ほかにもたくさんのことをして過ごすこと。
第3のS (Soothed──なだめられていること)親は子どもに、安全で、見守られていると感じながら、つらいときにはなだめられていると感じてもらいたい。子どもをなだめるとは、人生の海で必ず襲いかかってくる波を消し去ることではない。押し寄せてきた波に乗る方法を教え、子どもから必要とされたときそばにいることだ。
(感想:そうなんですよね。だから、ストレスや失敗しそうな状況をすべて取り除くことがいいわけでもないので、安心して失敗させてあげて、転んだらなぐさめることが大切ってことですかね〜)
第4のS(Secure──安心していること)安全で、見守られ、なだめられていると感じていれば、第4のS(Secure──安心していること)、つまり安心感につながる
いつでも寄り添ってくれると〝子どもが当てにできる存在〟になろう。あなたが、安全を守るためになんでもしてくれる、見守るために懸命に努力してくれる、思いどおりにいかないときにはそばにいてなだめてくれると信じられるようになれば、安心感が生まれるだろう。
「4つのS」は、子どもの脳を統合へ導き、柔軟性がある、ストレスを受けにくい神経系を構築する。結果として、子どもは、自分が安全で、豊かな人間関係と愛に恵まれ、避けられない困難にもうまく対処できると信じて、まわりの世界に安心と居心地のよさを感じながら生き抜く力を身につけていける。
ダニエル・J・シーゲル,ティナ・ペイン・ブライソン. 生き抜く力をはぐくむ 愛着の子育て (Japanese Edition) (p.27). Kindle 版. より引用
ということで、子どもに安全を提供して、間違った時失敗したときにはなだめて、手を出し過ぎず、安心を提供できる親になりたい!そう思いました。そのためには、親のエゴを満足させるためや、感情調整のために子供を利用してはならず、親も夫婦同士で、支え合うなどの愛着を大切にしていかないと寄り添えないですよねー。もうこの本は、最先端の知見プラスわかりやすいので、今年の子育て本としては、ずば抜けて1位でした。
第2位 Go Wild 野生の体を取り戻せ!

この本では、現代人が野生に戻る必要性を伝えておりその手段として、科学が教えるトレイルラン、低炭水化物食、マインドフルネスなどがあると述べています。登山・キャンプ・マインドフルネスを愛するぴのことしては、「私の好きなことに科学的に証明されているなんて!」という感じで感激しながら読みました。が、食事についての記述が多いのですが、ちょっとついていけなくて、低炭水化物食の話は華麗にスルーします(爆)
”最も重要な事実として、人間には生来、治癒力がそなわっていて、体は自ら病気を治せるのだ。つまり体には恒常性維持機能──生活上の労苦やストレスから体を回復させる複雑に入り組んだ機能──がそなわっている。それこそが、本書が言う「ゴー・ワイルド」の根幹なのだ。”
”今日わたしたちを苦しめている病の大半は、この文明病なのだ。”
"「野生」。それを今わたしたちは必要としている。"
ジョンJ.レイティ,リチャード・マニング. GO WILD 野生の体を取り戻せ! 科学が教えるトレイルラン、低炭水化物食、マインドフルネス (Japanese Edition) (Kindle の位置No.85-88). Kindle 版.
こういう時に気になるのが、ジョン・レイティーは、何者か?ということですよね。ハーバード大学医学大学院臨床精神医学准教授。神経精神医学の世界的な専門家ということですよ。信頼できそうじゃないですか。この先生は、運動こそが脳を鍛える!といった本も書いていましたね。
要するに、トレイルランやマインドフルネスで、野生の感覚を取り戻すと、より自然に・幸せに生きられるよという話でした。ボリューミーな本ですが、ご興味ある方は是非読んでください。別にトレランしなくても、キャンプで、歩くもとってもいい!んじゃ?と自分たちのやっているキャンプ・登山が正当化されるそんな本でした。食事のところは、スルーしちゃったので、中性脂肪も高いし、もう一度読もうかなあ・・・
第1位 恐れのない組織 「心理的安全性」が学習やイノベーションをもたらす エイミーC エドモンソン

最後は、心理的安全性です。もっといろいろ日本人が書いたわかりやすそうな本がでてますが、この本が、一番有名のようですね。
心理的安全性とは、大まかに言えば「みんなが気兼ねなく意見を述べることができ、自分らしくいられる文化」のことだ
要約:
2016年2月に『ニューヨーク・タイムズ・マガジン』にチャールズ・デュヒッグが記事を書き、「最高のチームをつくる要因は何か」を突きとめるためのグーグルでの五年にわたるプロジェクトを発表した。プロジェクト・アリストテレスというコードネームがつけられた。研究者たちは、5つの成功因子をみつけたが、その中でも「心理的安全性の重要性は群を抜いている」という結論に達した。
職場で従業員が本心を言わない(懸念や疑問を口にしない)のがおきまりのパターンであること、さらには、そのような人間らしい無意識にしてしまう反応が、およそどんな組織においても仕事の質に深刻な影響を及ぼしかねない。
いろいろな企業の心理的安全性が低いためにに起こった企業の失敗例が多数掲載されています。
フォルクスワーゲン社の不正、ウエルズ・ファーゴ、ノキアなどに起こった問題の背景は・・・・他のものは優れているのにもかかわらず、
「欠けていたのは、リーダーシップだ──心理的安全性が確実に職場に広がり、人々が社内の有力者に、本当のことを話せるようにするリーダーシップである」
福島原発の事故も、事前に危険性を予期していた報告がいくつかあったのに、その懸念を軽んじてしまった経緯があるんですって。
エイミー・C・エドモンドソン,村瀬俊朗. 恐れのない組織「心理的安全性」が学習・イノベーション・成長をもたらす (Japanese Edition) (p.111). Kindle 版.
まとめると、心理的安全性とは、職場の人間関係をのらりくらり仲良くするためのものではなく、いざ、大きな失敗がもたらされそうな時、その失敗について気づいた者が、上司などからの重圧にまけず「正直に話し出せるかどうか」「それを認める風土があるかどうか」であり、それによってより生産的な方向にシフトしていく可能性をもたらす重要なファクターということ。
ということで、最後は重たいテーマになってしまいましたが、むむむこれってすごく大事!。破壊王はなぜか英語で読んでて、私も日本語で読んで(無駄な書籍代)なんか二人で「大切な一冊だったね」と感想を語り合った一冊でした。方向性として失敗しそうなのに、上に忖度して、意見がいえない。そんな組織はもう時代遅れ・・・ということでしょうか・・・。
小さなチームでも、思ったことが自由にいいあえて、否定されない。特に自分が間違った方向に行きそうな時に、それを言い合えるそんなチームを来年は仕事で作っていきたいなーと思いました。それに加えて、インクルーシブ・ダイバーシティーそんな価値観を私は大切にしていきたい。
ということで、ぴのこの今年の5冊は、こんな感じでした。アウトドア大してないじゃん・・そう思われた方もいらっしゃったかもしれません。
まあ、色々読んでインパクトが残ったのがこうだったのよね、いうことで、最後までお読みいただきありがとうございました!
*インスタやってます。気軽にフォローお願いします。右サイドバーにアイコンあります。
登録してみました。よかったらクリックお願いします!↓
にほんブログ村
コメント
おはようございます。「アウトドア大して~」と書かれていますが、途中 ”野生に” も出てきましたが、本来生活そのものが家から1歩外に出たら ~out "door"~ ですもんね、組織のチームビルディングなどとても興味深く読みたくなる本の紹介でした。
(要約書いて頂いているので読まない可能性もありますが、)ありがとうございました。
(要約書いて頂いているので読まない可能性もありますが、)ありがとうございました。
やんちゃまけんたいさん
おはようございますー。たしかに、チーム組織もアウトドアですね(笑)チームビルディングの二冊目の本は、読みやすくておすすめですよ。なんか、私もできることあるかも!となる本でした。もう一冊でてる、1秒で話せ?も今読んでますが、面白いです。
野生はマニアックで、妙に熱いので、読むのに時間がかかってます(笑)
おはようございますー。たしかに、チーム組織もアウトドアですね(笑)チームビルディングの二冊目の本は、読みやすくておすすめですよ。なんか、私もできることあるかも!となる本でした。もう一冊でてる、1秒で話せ?も今読んでますが、面白いです。
野生はマニアックで、妙に熱いので、読むのに時間がかかってます(笑)
※会員のみコメントを受け付けております、ログインが必要です。